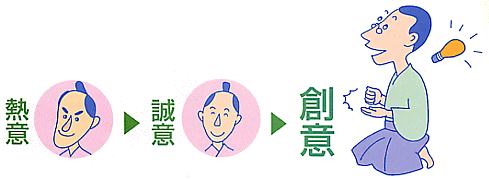江戸時代の湯の花が現代の入浴剤に
“ 明礬 ” の危機
これまで、1666年(寛文6年)渡辺五郎右衛門によって始まった別府の“明礬”づくりが脇儀助に引き継がれ、1730年(享保15年)以降は日本最大の産地になってゆく過程をお話しました。
ところが近世に至り、料学技術の進歩は化学染料を生み出します。
その結果、染色する際に明礬を必要としなくなったのです。
別府・明礬の地は大きな岐路に立たされます。
工業原料から “ 入浴剤 ” への変身
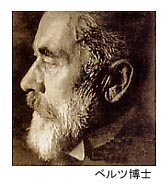 この時、野田村で森藩の湯の花を管理していたのが岩瀬保彦です。
この時、野田村で森藩の湯の花を管理していたのが岩瀬保彦です。
岩瀬は、この当時来日していたドイツのベルツ博士の「この地の明礬は温泉成分の結晶」という言葉に強い衝撃を受けるのでした。
岩瀬はこれまでは工業の原料としていた明礬を“湯の花”と命名し、入浴剤として全国に向けて売り出しました。
時に明治17年。
折からの銭湯ブームという追い風にも支えられ、“別府温泉の湯の花”はまたたく間に日本中を席巻することになったのです。
17世紀の半ばから衣服の染色の色止めや皮革加工の薬剤として用いられてきた“豊後明礬”は、180度その目的を変え、ここに人々の健康のために資する“別府温泉天然湯の花”として生まれ変わったのでした。
“ 熱意 ” “ 誠意 ” そして “ 創意 ”
湯の花物語にこれまで登場した三人の人物。
湯の花(明礬)製造の技術を開発した渡辺五郎右衛門を“熱意の人”とするならば、湯の花中興の祖脇儀助は“誠意の人”。
そして今日の入浴剤としての礎を築いた人物、湯の花生みの親岩瀬保彦は、まさに“創意の人”といえるでしょう。